家を相続することになったとき、どのように手続きを行えばいいのか、このまま住み続けるためにはどうしたらいいのか、売ることはできるのかなど、さまざまな疑問が浮かぶのではないでしょうか。


「相続で揉める話を耳にしたことがあるけれども自分は大丈夫だろうか…」、「相続税を払わなければならないことは知っているが、一体どのくらいの金額になるのだろう」と不安な気持ちもあるでしょう。
家の相続は、遺言書があれば基本的にその内容に従いますが、遺言書がなければ遺産分割協議を行うことになります。家の持ち主の配偶者であれば、配偶者居住権を使って住み続けることも選択肢の一つです。
もし家を引き継ぎたくないときは、相続を放棄するか、相続したあとに売却することもできます。
相続の手続きは、相続人の確認、遺産分割協議、名義の変更など非常に手間と時間がかかります。また、相続税がいくらになるのか確認するにも、家の評価額を確認したり、控除額を計算したりと、算出方法は複雑です。
この記事では家を相続する一連の流れを解説しますが、難しそうだからプロに頼りたいという方は税理士に相談すると良いでしょう。「ミツモア」であれば、相続に強い税理士を探すことができるので、ぜひ利用してみてください。
家の相続はすべき?しない方がいい?メリット・デメリット比較

家を相続すると慣れた家に住み続けることができますが、一方で相続税などの税金がかかるほか、住まなくなっても固定資産税や維持費を支払い続けなければならないというデメリットがあります。
反対に、相続放棄を申し出て家を相続しない、もしくは一旦相続してすぐに売却することにもメリットとデメリットがあります。
まず、家を相続することで発生するお金を払わなくて良いことがメリットです。家を引き継がなければ、当然家の維持費は発生しません。固定資産税と都市計画税を毎年払うこともなくなります。売却する場合は、その分の現金を得ることもできます。
一方で、相続を放棄するには他の財産も一緒に放棄しなければならないことがデメリットです。また売却する場合は、必ず相続登記で名義を変更したあとに売却の手続きを行わなければならないので手間がかかるほか、売却する際には譲渡所得税が課されます。
家を相続して住み続けるか悩んでいる方は、これらのメリット・デメリットも踏まえて検討しましょう。
相続する家の価値を知りたい場合は一括見積もり!
家を相続するかどうか判断するには、税金がいくらになるかや、どれくらいの金額で売却できるかがポイントになります。これらを確かめるには、家の価値を正しく知らなければなりません。
まず、相続する際に課される相続税や登録免許税の金額は、固定資産税評価額をもとに決まります。固定資産税評価額は市町村長によって決定され、固定資産課税台帳に登録されています。
どのくらいの金額で家を売却できるかを知るためには、専門家に査定してもらうと良いです。「ミツモア」を使えば、いくつかの簡単な質問に答えるだけで、不動産会社に無料で一括査定を依頼することができます。家にどれくらいの価値があるか知りたい方は、ぜひ利用してみてください。
家を相続する方法

家は、遺言書があればその内容に従って相続します。遺言書がなければ、その他の財産も含めて遺産分割協議を行って相続します。しかし遺産分割の結果、被相続人の配偶者が家に住めなくなる事態を防ぐために、配偶者居住権という制度があります。
この3点についてご説明します。
遺言書があればその内容に従う
遺言書が残されている場合、遺言書に書かれた内容が最優先となります。つまり、遺言書で特定の相続人に家を引き継ぐことが指定されていたら、原則としてそれに従います。そのため、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があり、遺言の種類や保管場所によって、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認する「検認」の手続きが必要となる場合があります。
検認が必要な遺言書は、勝手に開封してはならないので注意してください。検認が必要な遺言書は、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の2種類です。
遺産分割する
遺言書がないときは、相続人全員で「遺産分割協議」という話し合いをして家の相続の仕方を決めることになります。その他に相続する財産も含めて、現物分割、代償分割、換価分割、共有名義の4つの方法のいずれかで分割して相続します。
現物分割は、不動産を含む財産をそのままの形で相続する方法です。最もシンプルで手続きも簡単であり、各相続人が所有する家の管理を独立できることがメリットです。一方で、家の評価額に差があると不公平になり、相続人の間で不満が生まれる可能性もあります。
代償分割は、現物で財産を相続した人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。相続人の間での家の分割に関する争いを避けられ、住んでいる人がそのまま住み続けることもできます。しかし、代償金の合意形成が難航する可能性があるほか、代償金を支払うための現金が必要となります。
換価分割は、不動産を売却し、その代金を分割する方法です。家を現金化するため、家の管理や維持費の負担を回避できます。一方で、売却に伴う手数料や税金が発生するため、分割後の代金が元の家の価値と比べて減少する可能性があります。
共有名義とは、複数の相続人が不動産の所有権を共有する方法です。複数人が共同で家を所有するため、維持費などを分担することができます。しかし、家の売却や貸し出し、処分などの際に共有者全員の同意が必要なため、将来的にトラブルが生じるリスクがあります。
配偶者居住権を活用して住み続ける
配偶者居住権とは、被相続人の財産であった家、もしくは夫婦で共有していた家に、配偶者が住み続けられる権利のことです。住み続けられる期間は、原則として配偶者が亡くなるまでです。
以下の2点の要件を満たすと、配偶者居住権を取得できます。
- 配偶者が、被相続人の相続開始時に居住していたこと(※内縁の配偶者は含まない)
- 被相続人の遺言があること、もしくは配偶者が居住権を取得するという遺産分割がされたこと
また、被相続人により、他の相続人や第三者に家が遺贈された場合であっても、配偶者が最低6か月間は無償で住み続けられる「配偶者短期居住権」もあります。
配偶者居住権は、被相続人の財産であった家にもともと住んでいた配偶者が、生活に困らないように保護するための権利なのです。
家を相続しない方法 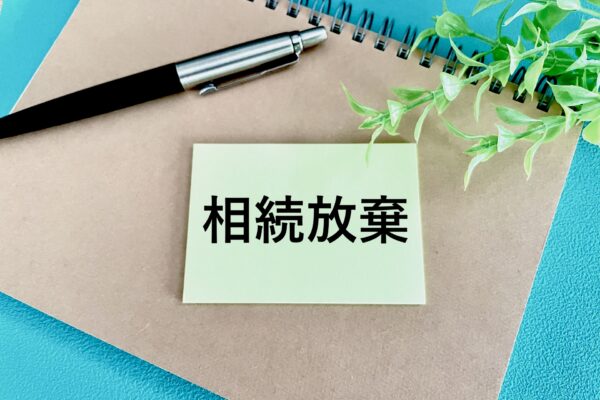
家を所有していた被相続人が亡くなったものの、相続税を払いたくない、家の維持費を負担したくないなどの理由から、家を相続したくない方もいらっしゃるのではないでしょうか。家を引き継ぎたくないときには、以下の選択肢があります。
この2つの方法を詳しく解説します。
相続放棄:資産と負債をすべて相続しない
相続放棄とは、被相続人の資産と負債をすべて相続しないことです。つまり、家だけ相続せずに他の財産は相続することはできません。
相続放棄を行うには、相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申し出なければなりません。相続開始前、すなわち被相続人が生きているうちに相続を放棄することはできません。また、一度相続を放棄すると、原則として撤回できないため注意が必要です。
他に相続したい財産がなく、家も相続したくない場合は相続放棄を検討すると良いでしょう。
一旦相続したのちに売却する
相続放棄はしたくないものの、家を引き継ぎたくない場合は、一旦相続したのちに売却することを検討しましょう。
売却すると、家の維持費を払う必要がなくなる、家を現金化できるなどのメリットがあります。
また一戸建てであれば、相続した家を3年以内に売却するときに、築年数や居住状況などの一定の要件を満たすと、3,000万円の特別控除を受けられる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を活用できる可能性があります。
なお、「空き家の3,000万円特別控除」は、被相続人の自宅である必要があります。そのため、投資用不動産の場合には適用されないことに注意しましょう。
同様に、売却するまでの間に事業や貸付用として使用してしまった場合も、この特例の適用対象外になりますので、注意が必要です。
家を相続する手順

家の相続は、次の流れで行います。
普段行うことがない手続きばかりで、聞きなれない用語も多いとだと思います。一つずつ丁寧に説明するので、内容を理解して少しでも早めに着手しましょう。
遺言書の有無を確認する
遺言書があればその内容に基づいて相続の手続きを進めなければならないため、まず初めに遺言書の有無を確認します。遺言書では、相続人や財産分割方法が指定されているケースがあります。
遺言書が残されていないときは相続人全員で遺産分割協議を行いますが、遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合は遺言書に従うことになります。
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があり、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認する「検認」の手続きが必要となります。
相続人を確定する
次に法定相続人を確定しましょう。法定相続人が誰かは、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を見ることで確認できます。
遺産分割協議のあとに新たな法定相続人がいると判明した場合、再度遺産分割を行わなければなりません。法定相続人の確定は慎重に実施しましょう。
相続財産を確認する
相続財産の確認も行いましょう。相続財産を一覧でまとめる「財産目録」も作成すると、相続手続きをスムーズに進められます。
財産目録には、プラスの財産とマイナスの財産をどちらも記載します。プラスの財産とは不動産や預貯金、自動車などで、マイナスの財産とは住宅ローン、家賃などです。
不動産が相続財産に含まれるかどうかは、市区町村から届く固定資産税の「課税明細書」で確認できます。もしくは市区町村の役所(東京23区は都税事務所)で取得できる「名寄帳」の写しでも確認可能です。
遺産分割協議を実施する
遺言書がない場合は遺産分割協議を行って相続人全員で遺産の分割について話し合い、合意形成を行いましょう。
遺産分割協議で財産の分割方法を決定したら、不動産やその他の財産を誰がどのように相続するか記載した遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員の記名捺印が必要です。
家の名義を変更する相続登記を行う
遺言書や遺産分割協議により不動産の相続人が決まったら、家の名義を被相続人から相続人に変更する「相続登記」という手続きが必要です。
相続登記は令和6年3月末まで任意とされていました。しかし、令和6年4月からは義務化されており、不動産を相続により取得した相続人は、所有権の取得を知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなくてはなりません。
また、相続登記を行う際には、登録免許税を払わなければなりません。相続の登録免許税の金額は、「固定資産税評価額×0.4%」です。その他に、戸籍謄本、住民票などの必要書類を取り寄せる費用も発生します。
相続税を申告・納付する
相続により家を取得した人は相続税の納税義務者となり、相続税の申告書の提出と納付を行わなければなりません。相続税の申告・納付の期限は、原則として相続人が相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
期限内に申告と納付を行わなければ、無申告加算税や延滞税がかかる、相続税に関する特例が適用できないというリスクがあるので注意してください。
ただし、いくつかの要件を満たせば延納が認められます。延納の要件は、相続税額が10万円を超えていること、申告期限までに延納申請書を提出することなどです。
家の相続で発生する税金や費用

家を相続する際に相続税がかかることは知っているけれども、どのくらいかかるのか、他に払わなければならない税金や費用があるのかと疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。
家を相続するときにかかる税金や費用は、以下のとおりです。
- 相続税:基礎控除額を超えた分に課される
- 登録免許税:固定資産税評価額×0.4%
- 司法書士への報酬:5〜15万円
- 雑費:必要書類の取り寄せ・郵送費用など
相続税:基礎控除額を超えた分に課される
相続税は基礎控除額を超えた分に課税されます。基礎控除額の求め方は以下のとおりです。
例えば相続人が配偶者1人と子3人であるとき、基礎控除額は「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となるので、5,400万円までの相続財産には相続税がかかりません。
基礎控除額を超えた分に対して相続税がいくら課されるかは、財産の金額によって決まります。相続税の税率は10%〜55%、さらにそこから控除される金額は0円〜7,200万円の間で変動します。
相続税の金額を知るには以下の手順を踏まなければならず、計算は非常に複雑です。
- 課税遺産総額を算出する(課税価格-基礎控除額)
- 相続税の総額を算出する(「課税遺産総額の法定相続分×相続税率」の総額)
- 各人の相続税額を算出する(相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額)
自分で計算するのは難しいと感じた方は、税理士に相談すると良いでしょう。「ミツモア」であれば、相続に強い税理士を探すことができるのでおすすめです。
登録免許税:固定資産税評価額×0.4%
登録免許税とは、家の登記を行うとき、すなわちに家の名義を変更するときに課される国税です。登録免許税をいくら払うかは、固定資産税評価額に税率をかけて決まります。固定資産税評価額は、都税事務所や県税事務所、市役所で閲覧できる固定資産課税台帳に記載されています。
相続における登録免許税の税率は、以下のとおりです。
なお、登録免許税の税率は贈与などケースによって異なります。
司法書士への報酬:5〜15万円
相続登記を依頼する、司法書士の方にも報酬を支払う必要があります。目安としては、5〜15万円です。
自身で相続登記をされる方もいますが、安心かつスムーズに相続登記を完了させるためには、司法書士に依頼することをおすすめします。
必要書類の取り寄せ・郵送費用
相続登記を行うには、住民票や戸籍謄本、登記申請書などの書類を準備しなければなりません。書類の取り寄せには各数百円の取得費用が発生します。例えば、住民票(除票)は1通300円、戸籍謄本(除籍抄本)は750円、固定資産評価証明書は200円〜400円ほどかかります。
加えて、必要書類を法務局へ送るための郵送費用も必要です。
家を相続するときのポイント

家を相続する際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
家の相続からしばらく経って将来的に損をしたり、後悔したりすることがないよう、この3点に注意しましょう。それぞれ詳しくご説明します。
相続登記を期限内に済ませる
令和6年4月1日から相続登記、すなわち相続財産の名義変更が義務化されました。家を相続したときは、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく期限内に登記しなかった場合、10万円以下の過料が科せられる対象となってしまいます。正当な理由として認められるのは、相続人が非常に多く、戸籍謄本などの必要書類の収集や他の相続人を把握するのに時間がかかってしまうケースなどです。
過料の対象とならないように、相続登記は早めに済ませましょう。
共同名義の場合全員の同意が必要となる
共同名義による相続の場合、売却時に共有者全員の同意が必要になりますので、同意を得るのに時間がかかる点にも注意しておきましょう。
また、共同名義の場合は、相続した資産の価値を共同名義者でどのように配分するか、なども議論しておく必要があります。
共同名義の場合も、前段の相続登記の期限は変わりありませんので、注意してください。
相続する家の価値を正しく把握する
家の価値を正しく把握することも重要です。相続時に課される相続税や登録免許税、家を持ち続けているとかかる固定資産税や都市計画税は、家の固定資産税評価額に一定の税率をかけて決まります。どのくらい税金を払うか知るために、固定資産税評価額を確認しましょう。
また、相続した家を売却した場合にどのくらいの金額になるかも知っておいた方が良いです。売却する際の家の価値を知ることで、「相続して売却した方が得だ」、「将来的に価値が上がりそうだから、税金を払ってでもまだ売らないでおこう」などの判断を下し易くなるからです。
家を売る場合の価値を知りたい方は、「ミツモア」で不動産会社に無料査定を依頼してみてください。
相続後も維持費がかかることを認識する
家の相続で注意したい2つ目のポイントは、相続した後もお金がかかることです。
まず税金は、相続時に相続税や登録免許税が課されるのみならず、相続後には固定資産税や都市計画税を毎年納めなければなりません。その他に、家を持ち続けるとなると、改修費用などの維持費も発生します。
相続した後に、思っていたよりもお金がかかってしまうという事態に陥らないよう、維持にかかる税金や費用をあらかじめ試算しておきましょう。
空き家になる可能性や売却時のトラブルを認識する
家を相続するときには、将来的に空き家となってしまう可能性や、売却時に起こりうるトラブルも認識しておいた方が良いです。
相続して自分が住んでいたとしても、さまざまな事情で住まなくなったときや自分の死後に空き家となるかもしれません。空き家になると、住んでいなくても税金が発生し続ける、劣化が進むことで将来的に修復費用が高額になるなどのリスクが生じます。
また、相続した家を売却する際に、他の相続人から反対されてトラブルに発展する可能性もゼロではありません。
これらのリスクも考慮したうえで、家の相続を検討することをおすすめします。
家の相続は税理士に相談しよう

家を相続するかしないか判断する際は、家の固定資産税評価額や売却額を把握したうえで、さまざまな要素を総合的に考えなければなりません。判断の要素となるのは、相続時に課される相続税の金額、相続した後の固定資産税や家の維持費、相続して売るときの金額、他の財産も併せて放棄するかなどです。
被相続人から家を引き継ぐには、遺言書に従うか、現物分割、代償分割、換価分割、共有名義の4つ方法で遺産を分割して相続する、配偶者居住権を使って住み続ける方法があります。一方で、家を引き継ぎたくない場合には、相続放棄や相続したあとに売却することを選択することになります。
相続の手続きは、相続人の確認、遺産分割協議、相続登記など慣れないものばかりです。相続税の算出にあたっても、家の評価額を確認したり、控除額を計算したりと非常に複雑で手間と時間がかかります。
相続は税金にかかわる重要な事柄だからこそ自分で進めようとせず、税理士に相談することがおすすめです。「ミツモア」であれば相続に強い税理士を探すことができるので、専門家に任せ安心して手続きを進めたい方は利用してみてください。
